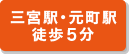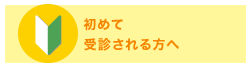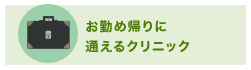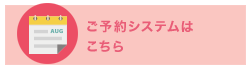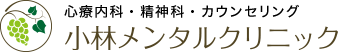小林俊三先生が神戸トアロードに「小林メンタルクリニック」を開業されることになりました。神戸大学在職中は2万人余の学生・職員の心身の健康をサポートする保健管理センターにおける「こころの健康相談」の中心的存在として活躍していただきました。心に病を抱える方々の話にじっくり耳を傾け、お薬に頼りすぎない診療をされることが特徴で、これは近年数少なくなってきている精神分析療法のエクスパートとして、小林先生が長年に渡る研鑽を積み重ねてこられたからこそ、できうることであるとも申せます。神戸大学でも10代の若者から60歳を超える職員まで、幅広い年齢層の方々の心の拠り所となられた先生が、今度は広く地域社会において市民の皆様の相談相手となられます。さらに多くの方々が、その診療に浴し、こころ救われて行かれることでしょう。


院長の紹介
神戸大学医学部附属病院
精神神経科・病棟医長の時代
大学病院に戻ってしばらく経った頃、病棟医長を拝命しました。この時期は、統合失調症、双極性障害、うつ病、摂食障害、パーソナリティ障害等の重症な方々と出会い、交流する貴重な機会となりました。
体重が20kgを切る拒食症の患者さんや、何度も自殺企図を繰り返す患者さんの心の中にも、人とつながり助けを求める部分(ここでは「幼い子ども」と呼びましょう)が生きています。
その「幼い子ども」が治療者とつながることを妨害する、強力な別の部分(ここでは「恐いボス」と呼びましょう)も存在します。「幼い子ども」が治療者に助けを求めようとすると、「恐いボス」はその動きを察知し妨害しようとします。「幼い子ども」を心の中で閉じ込めて、治療者と触れ合わないようにさせるのです。「恐いボス」がどのような場面でどのように働くのかを理解し、治療者が助けを求めている部分としっかり触れ合うことが要となります。
こうした患者さんの内側の各部分の関係が、治療チーム全体の関係によって包容されることが必要です。したがって、治療チームの中で生きた対話が繰り返され、それらが患者さんを理解することに戻されるプロセスが大切になります。これらのことを深く学んだのがこの時代です。


神戸大学保健管理センター准教授の時代
保健管理センター「こころの健康相談」の責任者として、学生・教職員の治療(投薬を含む)に11年間従事しました。この時代に、ハラスメント被害解決のシステムや、メンタルヘルス失調からの職場復帰支援システム(試し出勤、復職判定委員会、リハビリ勤務等)の作成に尽力しました。
例えば、誰かが過酷な超過勤務の末にうつ病を発症し、内服治療によってもなかなかよくならない、としましょう。その背景として、上司を含む複雑な職場の人間関係が絡んでいることがしばしばあります。また、そのような関係に対してはっきり自己主張できない理由の一つとして、家族歴、生育歴、パーソナリティ形成の問題等が隠れていることもあります。これらの問題を全体的に有機的に理解し、介入することが肝要となります。様々な事例への対応を通して、各研究科の方々とは密接で深い信頼関係を築くことができました。このことは現在も私の財産となっています。

精神療法の訓練

【 経 歴 】
【 資格・所属学会 】
- 精神保健指定医
- 日本精神神経学会専門医
- 日本精神分析協会候補生
- 日本精神分析学会認定精神療法医
- 日本精神分析的精神医学会運営委員
- 日本医師会認定産業医